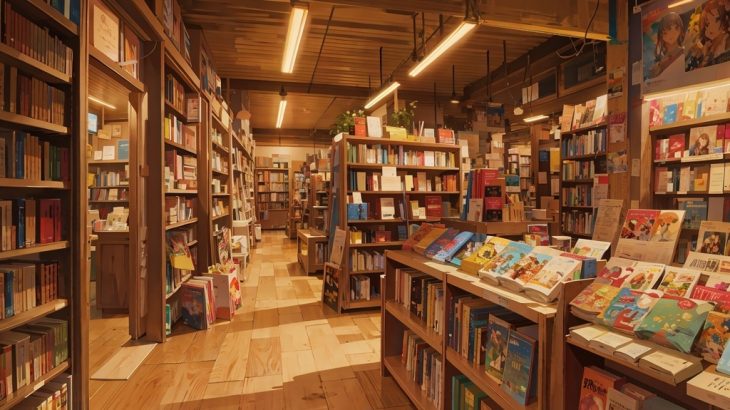出版業界の調査研究機関である全国出版協会・出版科学研究所は、2024年(1~12月期累計)の出版市場規模を『季刊 出版指標』2025年冬号で発表しました。2024年の紙の出版物の推定販売金額は前年比5.2%減の1兆56億円です。内訳は書籍が同4.2%減の5,937億円、雑誌が同6.8%減の4,119億円となっています。
紙の出版物の売上高が年々落ち込んでいる主な原因として、書店数の減少が挙げられます。前掲の研究所が2024年に発表した資料によれば、2003年には約2万1千店舗あった全国の書店数は、2023年には約1万1千店舗と20年間で約半減しています。これに加えて、一般財団法人出版文化産業振興財団によると、書店がまったくない市町村は全体の約27.7%を占め、書店がないか、1軒しかない市町村は約47.4%にも及んでいます。
また、書店が閉店する背景には、スマートフォンやゲーム、SNSの普及による読書離れの深刻化、ネット書店や電子書籍の台頭など、さまざまな要因が絡んでいます。このように、現在では全国で書店数が減少の一途をたどっています。
この現状を打破するために重要なカギを握るのが「デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)」です。経済産業省の「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX 推進ガイドライン)」では、DXを以下のように定義づけしています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
書店の閉店が相次ぐ現状に歯止めをかけ、地域における書店の需要を高めるためにはDX(デジタルトランスフォーメーション)化の推進が欠かせません。一例として、AIの活用が書店数の減少防止に貢献することが挙げられます。
そこで本記事では、書店業界におけるDXに着目し、その課題やメリット、デメリット、そして国内外における実際の導入事例を紹介し、実態を明らかにしていきます。
書店業界のDX化における課題
紙の書籍を扱う書店業界は、アナログな企業だとされています。各企業がDX化に向けてさまざまな取り組みを進めていますが、ほかの業界と比べると依然として進んでいません。まずは、書店業界のDX化が進んでいない理由について解説します。
1.厳しい経営状況
書店にDX化をもたらすには、最新のデジタルツールやシステムを導入するためのハードウェアやソフトウェアの購入が必要です。しかし、現在の書店の多くは来客数の減少により売上高が低下しており、厳しい経営状況を強いられています。そのため、書店には初期費用のコストをかけられるほどの余裕がありません。
2.店舗・企業頼りの人材育成
新しいシステムやツールを導入した際は、従業員が新たなシステムを使いこなす必要があります。そのため、研修の実施、システムのマニュアル作成などが重要です。効果的な研修を行い、継続的に従業員を育成することによって、書店のDX化が進展していきます。しかし、これらを取り組む際には多大な時間・費用がかかり、人材の育成やマニュアル作成は店舗・企業頼りになってしまうという課題があります。
書店業界がDX化するメリットとデメリット
メリット
1.人件費削減、人手不足解消
DX化の具体例として、セルフレジの導入やスマートロックを利用した無人店舗の開店が挙げられます。これにより、レジ作業や店舗の開閉作業に従事する店員の人数を減らすことができ、人件費の削減が可能です。
2.在庫管理の効率化
商品在庫をデータ化する在庫管理システムを導入することで、在庫管理にかかる時間と人件費の削減が可能です。また、書店の利用客に向けた在庫管理システムも利便性が高いです。このシステムは、指定した書籍について、在庫の有無、在庫がある棚の番号、電子書籍の注文コードなどを調べることができ、顧客の求める情報をいつでも即時に提供します。
3.顧客体験の向上
書籍の人気ランキングや書籍紹介ポップを電子ペーパー(電子棚札)などで掲載することにより、リアルタイムで本の情報を確認可能です。また、顧客が購入した本の傾向を分析し、関連書籍を紹介する機能を導入することで、顧客一人当たりの単価の上昇が期待できます。
デメリット
1.システム導入時の費用
書店のDX化を図る際、費用面の負担が大きいことがデメリットのひとつです。インターネットを利用するための高速ネットワーク環境の構築をはじめ、在庫管理に必要なツールやシステムなどを準備しなくてはならず、多額の費用が発生する傾向にあります。
2.データセキュリティの懸念
DX化を進めるうえで、契約書や顧客の個人情報をデータで管理するため、セキュリティ対策を強化する必要があります。特に書店業界は、顧客の個人情報や業務データなどを取り扱うため、厳重な管理体制が求められます。ずさんな管理では、企業に対しての不信感は募り、信用を失ってしまう可能性もあります。企業を守るためにも、個人情報の取り扱いには十分な注意が必須です。
3.無人営業の万引き
スマートロックなどを利用した無人営業の店舗では、従業員が常駐していないため万引きのリスクが高いです。監視カメラやセンサー技術による防犯対策が進んでいるものの、完全に万引きを防ぐことは難しい現状があります。
書店業界におけるDX導入事例
ここからは書店業界のDX導入の例を紹介します。
1.予約システム
予約システムは予約受付→決済→顧客管理→集客まですべて自動化し、データ管理の効率化を可能にします。
「RESERVA(レゼルバ)」は導入数35万社を超える、業界トップシェアのクラウド型予約システムです。利用業態は350種類以上にのぼり、最短3分でサイトを作成できるシンプルな操作性が高く評価されています。無料のフリープランから利用でき、初めて予約システムを導入する方にもおすすめです。
書店の運営におすすめの機能として、しおりやブックカバー、袋など、書籍の購入時に追加したいサービスを予め選択できるオプション機能や、予約時に事前にオンラインカード決済が済ませられるレゼルバペイメントなどが挙げられます。これらによって、顧客の利便性と書店員の予約にかかわる煩雑な業務を大幅に改善します。
参考サイト:RESERVA公式サイト「書籍販売のための予約システム」
2.オンラインとオフラインを融合させた消費体験
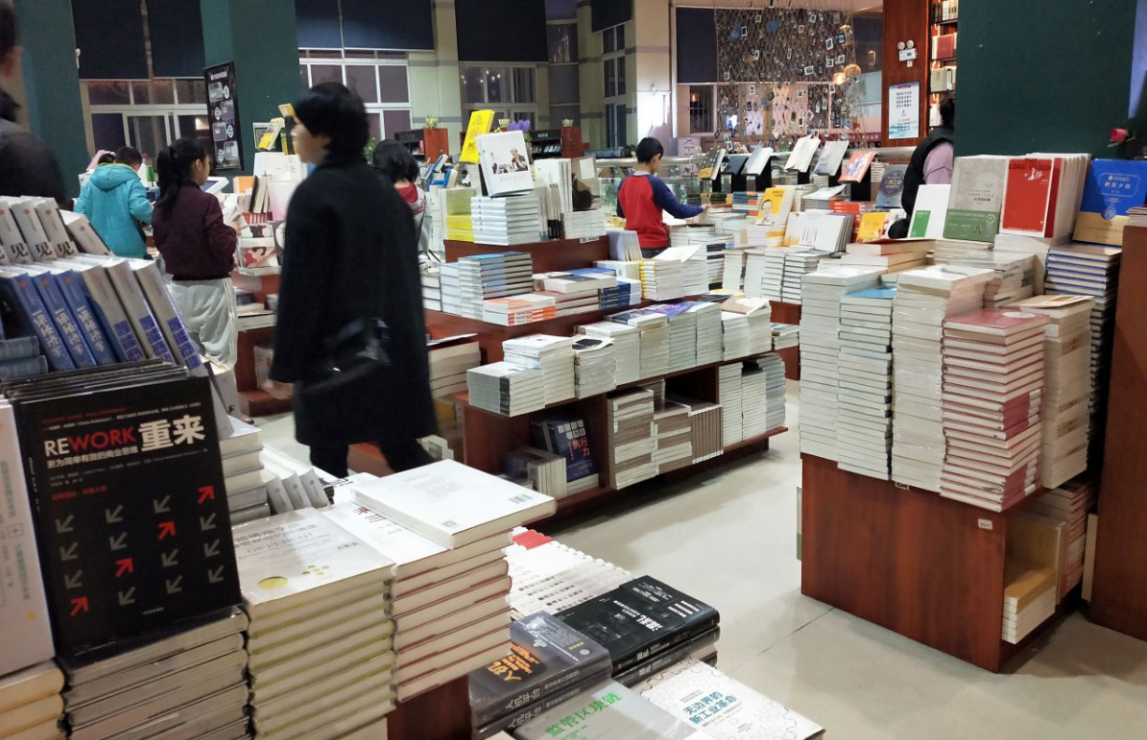
2017年に新華書店は、Alibaba Cloud(アリババクラウド)と提携し、DX化を行うことを発表しました。新華書店は中国の書店チェーンで、大都市から小都市までおよそ12,000店を展開しています。同社では、まず一部店舗で「ニューリテール化」と称し、店舗改造を行いました。
具体的な取り組みとして、本をまとめて置くだけで支払う値段がわかる無人レジ、顔認証すると購入履歴からおすすめの本が紹介される案内端末、QRコードやバーコードが表示されたタグをスキャンすると、オンラインショップの該当の商品のページが表示されるシステムの導入などが挙げられます。
参考ページ:ソフトバンク「本のニューリテールを実現する「新華書店」のDX化手法」
3.スマートロック・セルフレジを利用した無人販売

「ふうせんかずら」は、奈良県奈良市東城戸町にある無人のシェア型書店です。全国初のキャッシュレス無人書店として2018年にオープンしました。古本や新刊、オリジナル雑貨などを販売しています。
この店舗は、無人営業時にはIDナンバーを使ってセルフ入店が可能です。利用客は、無料のメンバー登録でIDナンバーを取得したうえで、ドアの番号キーにIDナンバーを入力すると開錠します。また、支払方法にキャッシュレス決済を導入しており、利用客は自身が希望する方法で決済できます。
このように、セルフレジやスマートロックなどを導入し書店をDX化することにより、人件費を削減しつつ書店を運営することが可能です。
参考サイト:無人&シェア型書店ふうせんかずら TOP
まとめ
今後の書店業界は現在より経営が厳しいものになることが予想されます。しかし、DX化を推進することによって在庫管理の効率化、人件費の削減が可能です。読書離れや電子書籍の影響による書店数の減少を対策するためにもDX化が欠かせません。